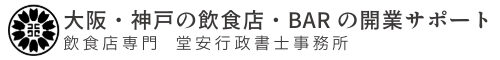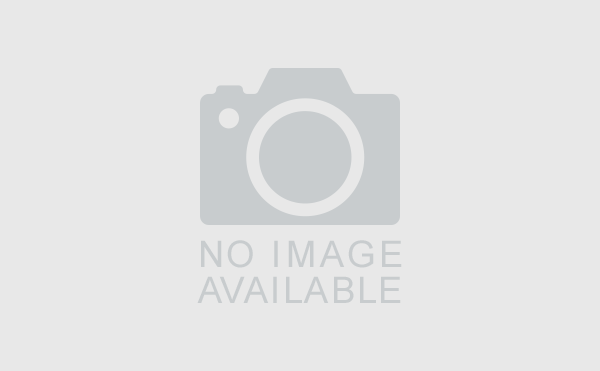深夜酒類提供飲食店(BAR)の法的な注意事項
令和7年 6月28日 風営法改正が施行されます。
主に風俗営業に関する業界が揺れ動く中、
BARなどのオーナー様にも少なからず影響はあるのではないでしょうか。
そこで、BARなどのオーナー様が知っておくべき法的な注意事項について、5つの事項に分けてまとめました。
①接待行為の危険性
接待は関係ないと思っていてもオーナー様は知っておくべき知識です。
風俗営業の無許可は風営法では一番重い罰則です。最優先で注意すべき事項です。
接待行為とは 接待に該当することを店側から積極的に働きかける行為を言います。
そして、近年判断が難しいのが、お客さんもそのような行為を期待して来店するようなお店のシステムも接待行為に当たるとされてます。
接待行為については詳しくは関連事項をご覧ください。
関連事項:接待行為について
特に今回の法改正で接待行為が発覚し、無許可営業となると
5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(個人の場合)
となり、非常に罰則が重くなっています。
風営法改正が行われた直後は、警察の見回りが厳しくなる可能性があります。また近年では細かいことで指導されたというケースも多くなってきており、より一層注意が必要です。
発覚するケースは、
・トラブルがあった時の警察対応による発覚
・お客さんや近隣住民、同業者からの通報 等が多く、
また一度指導などで目をつけられてしまうと、定期的に警察が見回りに来てしまうなどの事態にもなりかねません。
長期的に見て接待行為の有無を問うような営業方法やシステムであるなら、この機に見直しすることをお勧めします。
②客引き行為等禁止についての理解
客引き行為等とは、
・客引き行為:相手を特定して客になるように勧誘することで、立ちふさがる・付きまとう行為
・勧誘行為:特定の相手を役務に従事を誘ういわゆるスカウト行為
・客待ち行為:勧誘や客引きをするため待つ行為
上記3つの行為をする、または従業員などにさせる行為が禁止です。
それに対して、単に通行人に対し呼び掛け、相手の反応を待つのみでは客引きに当たらず(✖積極的に勧めたりする)
また、不特定多数の人に対するチラシ等の配布や自店舗前での呼び込み(特定の個人を呼び止めて交渉せずに、不特定多数の通行人に対して呼びかける行為)も上記行為に当たらないとされています。
厳密にはこのようなルールがありますが、わかりにくく曖昧な部分も多いのが現状です。
また、発覚するケースは、私服の警察官いわゆる覆面調査官での現行犯が多いです。
結論としては客引き行為はしない営業方法にすることが長く健全な経営には大切です。
③深夜に遊興行為の禁止
遊興とは、
•ショー、ダンス、その他興行等を見せる、または参加させる行為
•歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
•遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
•カラオケ装置で不特定の客に歌うことを勧奨し、合いの手等を行い、歌を褒めはやす行為
•スポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為 など
対照的に、遊興に当たらないのは、単にカラオケやビリヤードなどを客が自由に使用させる行為、スポーツ観戦をただ見せる行為など
勘違いしやすいのは遊興行為は、深夜(0時から6時まで)にしてはいけないという事です。
夜中の近隣の方の迷惑や、遊興の無許可営業にならないためにも最低限知っておきましょう。
④深夜に未成年の雇用または入店
深夜酒類提供飲食店では未成年(18歳未満)を雇用しても良いですが22時以降は働かせてはいけません。
また、22時以前でも未成年に酒類を提供させてはいけません。厳密には、お酒を作ったり注いだりするのは禁止で、運ぶだけならOKです。
ですが、未成年をBARなどで働かせているというだけで警察に目を付けられることにもなりかねないので、基本的には禁止が無難です。
お客さんの入店については酒類を提供する店では、原則18歳未満の入店が禁止されています。
ただし、原則なので例外があり、家庭の事情などにより未成年者が保護者と一緒に来店する場合は、地域によっては特例として入店できることもあるので、店舗でのルールを決めておくことが大切です。(こちらも色々な条例やモラルが絡んでくるので、BARであれば入店させないルールが無難です。)
◎事前に貼り紙などの告知をしているとトラブルを防げるでしょう。
また、たばこの喫煙可能な場所は客・従業員ともに20歳未満は立ち入り禁止です。
もちろん20歳未満への酒類の提供は禁止です。
⑤迷惑行為防止条例などの対策
迷惑行為に繋がるような行為は防止するよう、対策しなければなりません。
・泥酔者への酒類提供
・周辺での騒ぐ、暴れる、器物を破損するなどの行為
・その他他人に及ぼす迷惑行為
上記の行為をお断りするよう、店内やドアなどに張り紙などの対策が必要です。
◎他にも問題が起きた時の対応手順やルールなどを事前に、決めておくことにより、トラブルの冷静な対処が可能となります。
苦情受理記録簿の保管
・お店に苦情があると、受理年月日や苦情申出者の名前や連絡先、内容などを記録し、3年間保存しなければなりません。
従業者名簿の保菅
・一度でも従事した者(派遣や体験など含む)についての氏名などの情報を記録し、退職の日から起算して3年間保存しなければなりません。
以上です。
地域により追加のルールもあれば、微妙に違っている条例などもありますが、より良いお店にしていくには、基本的な法の知識は不可欠な要素です。この法改正の機会にルールを見直してみるのも良いかもしれません。
長く健全な営業に少しでも力になれたら幸いです。